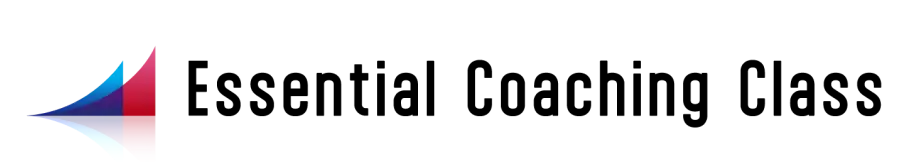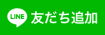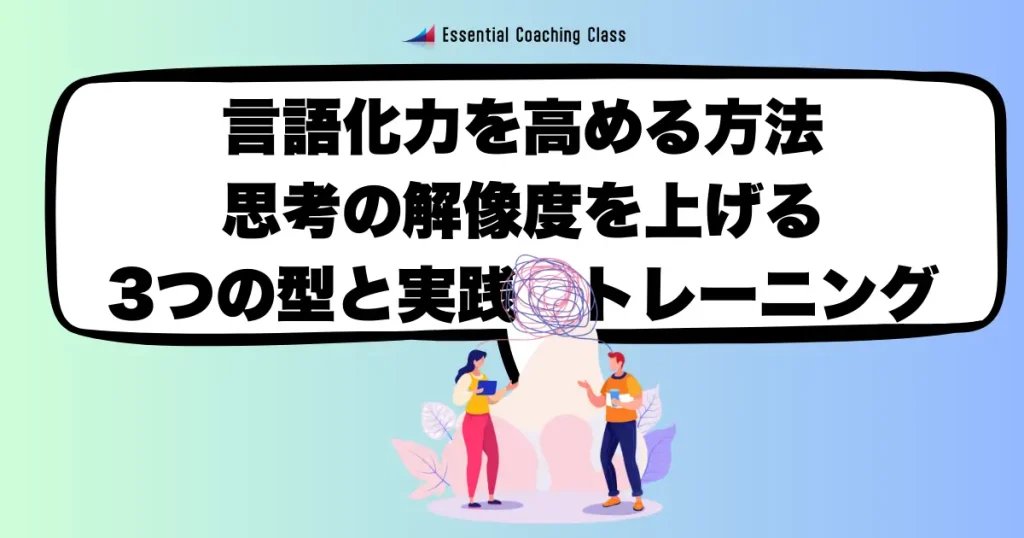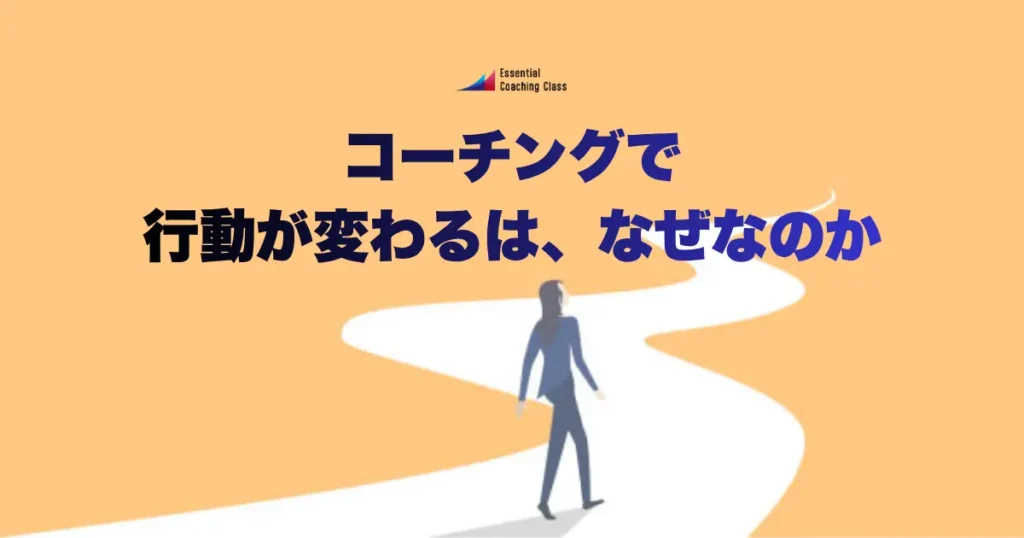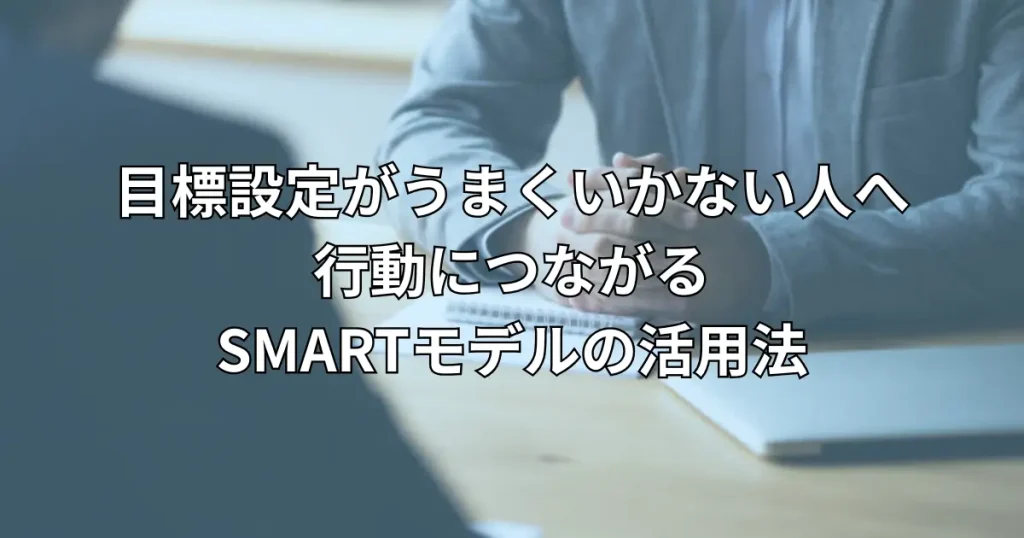コーチングという言葉は、ビジネスや教育、スポーツなど、あらゆる分野で使われています。
しかし「コーチングとは何か」と問われると、多くの人が「相手を励ますこと」「話を聞くこと」といったあいまいなイメージで捉えがちです。
本稿では、国際的に定義されたコーチングの意味から、その構造、誕生の背景を整理します。
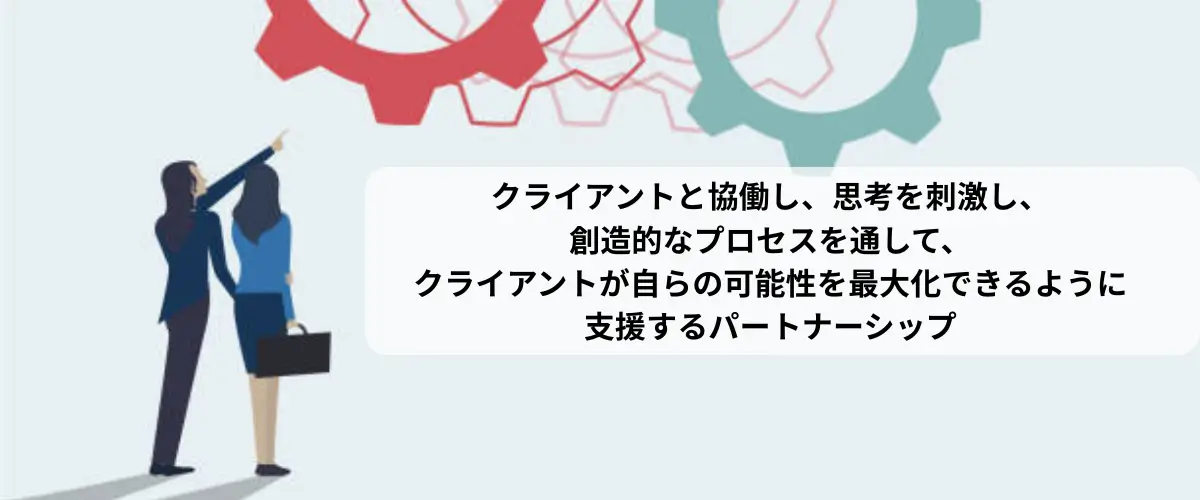
コーチングの定義 ― 世界基準から見た本来の意味
コーチングの定義や理論は、スクールの数だけ存在します。ですが、業界発展にもっとも貢献してきた団体は、国際的なコーチング団体であるICF(国際コーチング連盟)やEMCC(欧州メンタリング&コーチング協議会)ではないでしょうか。まずは、国際的な団体の定義をもとに、コーチングの本来の意味を理解していきましょう。
ICF(International Coaching Federation)は、コーチングを次のように定義しています。
「クライアントと協働し、思考を刺激し、創造的なプロセスを通して、クライアントが自らの可能性を最大化できるように支援するパートナーシップ」。
コーチングとは、「指導」や「助言」ではなく、対話を通じて相手の思考を促し、自ら答えを見つけていくための支援です。
このプロセスの目的は、「正解を教えること」ではなく、「本人が主体的に行動できる状態をつくること」です。
コーチングが教育やカウンセリングと異なるのは、「過去を掘り下げること」よりも「未来を設計すること」に焦点を当てる点にあります。
コーチングの誕生と発展 ― スポーツからビジネスへ
コーチングのルーツといえるものは、展開している理論によって様々です。ここでは、国際コーチング連盟のながれをみていきます。
コーチングの起源は、1970年代のスポーツ心理学にあります。
とくに有名なのが、テニスコーチのティモシー・ガルウェイによる著書『インナーテニス(The Inner Game of Tennis)』です。
彼は、プレイヤーが最高のパフォーマンスを発揮できないのは技術の不足ではなく、自分自身への過剰な評価や恐れが妨げていると考えました。
そこで彼は「どうすれば上手く打てるか」ではなく、「いかに内なる声に気づき、自分の感覚を信じて動けるか」に焦点を当てました。
この「無意識に起きている状態」を扱うアプローチが、現代コーチングの原型でもあります。
また、コーチ養成スクールの立役者といえば、トマス・レナードの名前があがります。1980年代初頭、後にコーチングの基礎を築くトマス・レナードは、「ランドマーク・エデュケーション」という自己啓発の教育プログラムをスタートさせました。その後、プログラムを受講した卒業生が、養成スクールを立ち上げると、レナードも競合となるスクールや団体を次々に設立。
詳しい歴史・変遷をまとめたコラムはこちら
2012年初版と少し古いですが、英治出版から発行されている書籍『コーチングのすべてーその成り立ち・流派・理論から実践の指針まで』にも歴史背景が記載されています。
日本には、2,000年前後から様々なスクールや団体が設立され、国際コーチング連盟も2008年に日本支社がたちあがりました。
国際コーチング連盟のサイトでは、コーチングにおける定義や優れたコーチの行動特性をまとめたコンピテンシーも公に公開されており、コーチングの質の維持に貢献しています。
ここでは、国際コーチング連盟に関するながれをご紹介しました。現在、日本で展開されているコーチングは様々な理論背景をベースに展開されており、今回ご紹介した国際コーチング連盟の定義に合致しないものもあるでしょう。
どのようなコーチングがご自身のスタイルにあうのか。検討する側もみているスクールや団体には、どのような特徴があるのかを見定めることが大切です。
コーチングは、様々な理論やスキルに支えられていると感じています。
・カールロジャース/アドラー/フロイト/ユングなどの臨床から始まった心理学領域
・認知科学、脳科学、成人発達理論、心理学理論
・NLP,ACTなどのセラピー
・コミュニケーションスキル
・言語学
人の行動を変容させるには、人についての理解が不可欠です

コーチングの基本構造 ― 信頼・目標・ギャップ・行動・実現
「コーチングの構造」とは、コーチングという対話的プロセスがどのような要素で成り立っているのかを明確に示す概念です。構造を理解すると、「なぜうまくいくコーチング」と「形だけのコーチング」があるのか。その違いがはっきり見えるようになります。
1. コーチングの基本構造 ― 3層モデル
コーチングの構造は、「関係」→「プロセス」→「技法」の三層でとらえるのが最も本質的です。
| 層 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ① 関係構造 (Relational Structure) | コーチとクライアントの間に築かれる心理的安全性・信頼関係。 | 「話しても大丈夫」「受け止められている」という感覚を生み、探索を可能にする。 |
| ② プロセス構造 (Process Structure) | 対話がどのように展開し、気づき・行動に至るかの流れ。 例:現状理解 → 目的明確化 → 意味づけ → 行動設計 → 振り返り。 | 思考の整理や行動変容を促す。 |
| ③ 技法構造 (Methodological Structure) | 質問、フィードバック、リフレクション、沈黙などの技法。 | 対話を深め、気づきを言語化・行動化する。 |
効果的なコーチングは、次の5つのステップで構成されます。
- 信頼関係の構築
コーチングの出発点は「安心して話せる関係」です。
コーチは評価や助言をせず、相手の話を遮らずに聴くことで、心理的な安全を確保します。 - 目標の設定
クライアントが望む未来や状態を具体的に描きます。
「いつまでに」「どのような状態を」「どんな意味で実現したいのか」を言語化することで、思考の焦点が定まります。 - 現状の把握とギャップの明確化
目標と現状を比較することで、行動すべき方向と課題が浮き彫りになります。
この「ギャップの可視化」は、脳に“動機づけ”を生む重要な段階です。 - 行動計画の立案
ギャップを埋めるために、今できる小さな行動を設定します。
行動が現実を変える唯一の手段であり、実践を通じて気づきが深まります。 - 実現と振り返り
実行した結果を一緒に振り返り、何が効果的だったかを整理します。
成功体験や改善点を確認することで、次の行動に自信と再現性が生まれます。
対話で整理された状態から「行動→振り返り→新たな気づき→再行動」というサイクルを繰り返すことで、相手は自分の可能性を徐々に広げていきます。
コーチングのプロセスでは、対話の中で描かれた未来のゴールに向かって、クライアントが実際に行動を起こすことが何より大切です。
「話してスッキリした」「やる気が出た」で終わるのではなく、現実の行動がどう変化したのかに注目します。
そして、現実の変化から何を感じ、どんな思考が生まれ、どんな意味づけがなされたのか――
そのプロセスをコーチとともに振り返り、磨き続けることが成長へとつながります。
コーチングとは、相手が自らの可能性を最大化し続けるためのプロセスに伴走するパートナーシップです。
目的は「良い話をすること」ではなく、自分の力で現実を動かし、その経験からさらに自己を進化させていくこと。
コーチングの成果は言葉の中ではなく、現実の変化の中に現れます。

コーチングが他の手法と異なる点
ティーチング(教える)、カウンセリング(支える)、メンタリング(勇気付け)との違いを整理し、コーチングの独自性を明確にします。
| 手法 | 内容 |
|---|---|
| ティーチング(Teaching) | 知識や技術を教える指導です。 |
| カウンセリング(Counseling) | 過去の出来事や感情を扱い、心理的回復を目指します。 |
| メンタリング(Mentoring) | 経験者が助言や方向性を示し、勇気づけを行い後輩を支援します。 |
| コーチング(Coaching) | 本人の中にある力を引き出し、未来を自分で創る支援です。 |
コーチングは「他人の答えを与える」のではなく、「相手自らが、自分の中にある答えを見つける」ための技術です。
この違いが、相手の主体性と行動力を高める鍵になります。
コーチングが目指すもの ― 可能性を最大化する支援
コーチングとは、信頼関係という土台の上に成り立つ、目的達成と自己理解を促す対話のプロセスです。
その対話を通じて、相手の認知・感情・行動の三層が統合的に変化し、内面からの成長が生まれます。
私自身、2009年にコーチングと出会って以来、「未来に視点を置き、自らの可能性を信じて行動する力」を実感し続けてきました。
コーチングによって育まれるこの力は、どんな環境でも通用する一生涯のスキルです。
コーチングは、感覚や精神論ではなく、科学的で再現性のある“対話の技術”。
その根底には、「人は本来、自ら成長する力を持っている」という人間への深い信頼が根底にあると私たちは考えています。
次の記事:なぜコーチングで行動変容がおきるのか