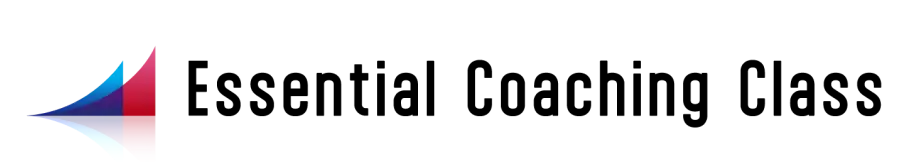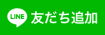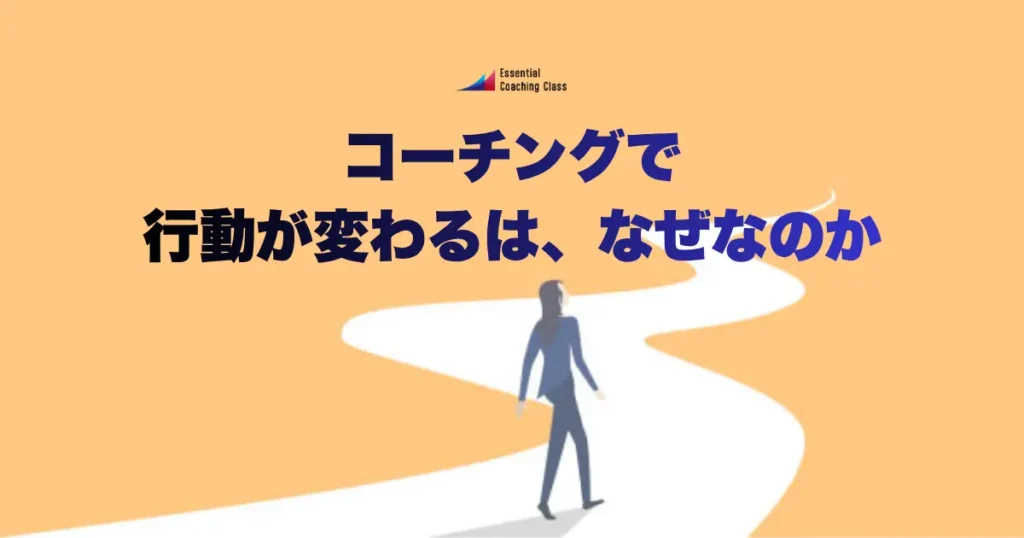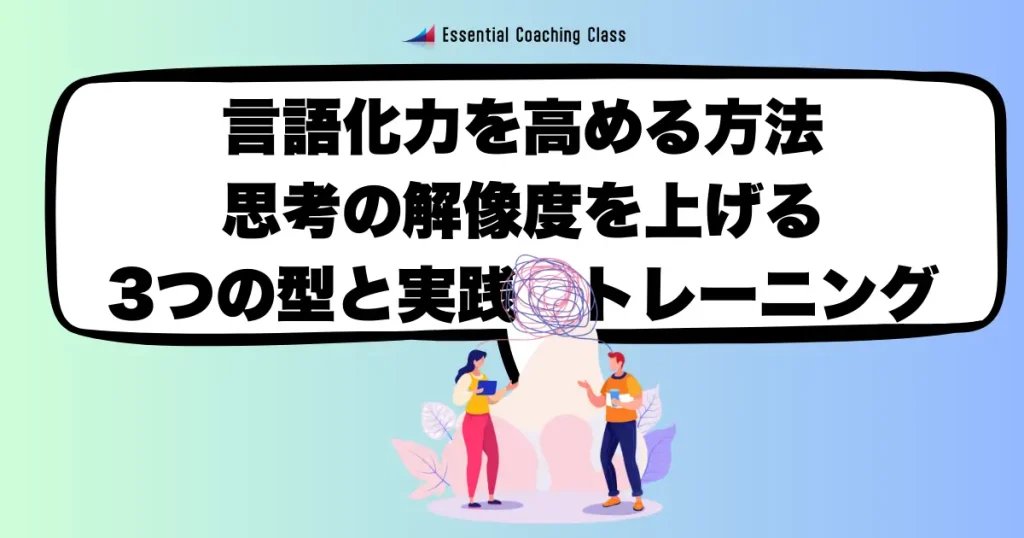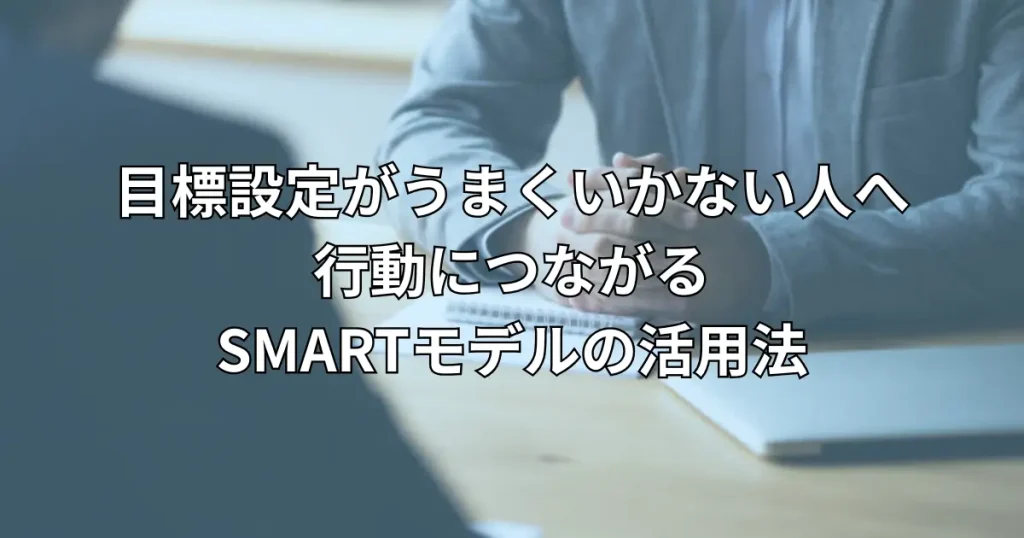「人は、話すだけで本当に行動を変えられるのでしょうか?」
コーチングを受けた人が実際に行動を起こし、習慣を変えていくのは偶然ではありません。
その背景には、人の脳と心の働きが密接に関係しています。
コーチングは、一時的な行動変化を起こすことも可能ですが、あたらしい行動への定着までを支援します。本稿では、単なる行動変化のみならず、行動変容を中心に解説していきます。
行動変容の基本構造と、脳のしくみから見た「人が変わる」プロセスを一緒に深めていきましょう。
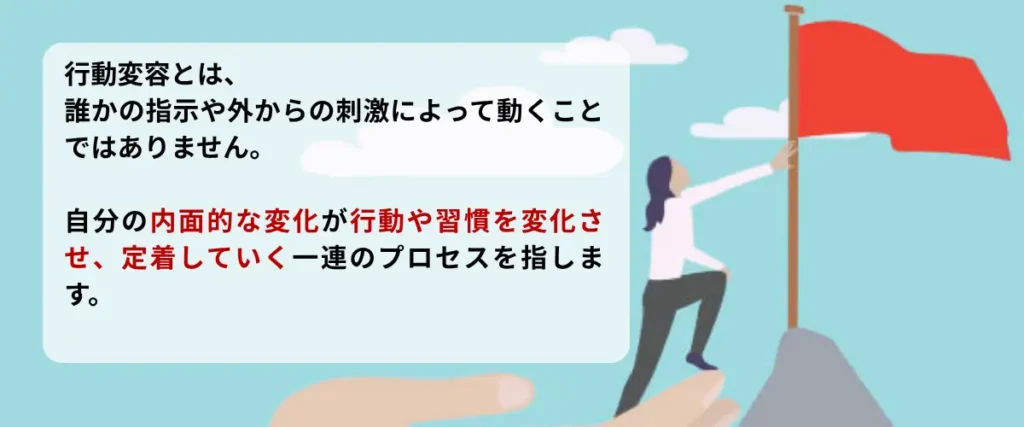
行動変容は「内側の構造変化」から始まる
行動変容とは、誰かの指示や外からの刺激によって動くことではありません。
自分の考え方や感じ方が変わり、ものごとの受け止め方が変化する。結果として、内面的な変化が行動や習慣を変化させ、定着していく一連のプロセスを指します。
「あの人なんか変わったよね」と言われるそのとき。変化は、表面の行動だけでなく、思考や信念のレベルで起きています。
「思考」「感情」「信念」「価値観」の変化。コーチングはこの構造のすべてに介入していきます。
| 層 | 変化の内容 | コーチングのアプローチ |
|---|---|---|
| 表層(行動) | 行動の仕方やタイミング、習慣の形成 | 目標設定、行動計画、実行支援 |
| 中層(思考・認知) | 物事の捉え方、判断の仕方 | 質問による認知の再構築(リフレーミング) |
| 深層(信念・価値観) | 自分や他者、世界に対する根本的な信じ込み | 内省的な対話を通じた自己理解とメタ認知 |
たとえば「失敗してはいけない」という信念を持つ人は、新しい挑戦を避けやすくなります。
このような深層の信念が変わらなければ、いくら知識を学んでも行動は変わりません。
コーチングは、「なぜそう考えるのか」「その考えが形成されたきっかけはなにか」「別の捉え方に変えると何が見えるか」と問いかけを行っていきます。思考の枠を揺らしながら、本人が自らの認知パターンに気づけるようにコーチは、相手の言動の背景を洞察していきます。
自分では、当たり前すぎて気づかない領域の可能性の最大化を阻む要因に介入する
このアプローチが、思考の選択肢を増やし、行動を変えるきっかけをつくっていきます。
脳内の情報が変わると行動が変わる ― 神経科学が示す3つのメカニズム
行動変容は、意志の強さだけで起きるものではありません。
脳の働き方そのものが変化することで、人は新しい行動をとるようになる。ここでは、神経科学から見た「コーチングが行動を生む3つの仕組み」を一緒にみていきましょう。
① メタ認知の活性化 ― 自分の思考を観察する力
メタ認知とは、「自分が何をどう考えているのかを自覚する力」です。
コーチが「どう考えた?」「なぜそう思った?」と問いかけると、
クライアントは自分の思考を外から見るようになります。
このとき、自己モニタリングに関わる前頭前皮質などの脳領域が活性化します。
脳科学では、この領域が働くことで、感情や衝動に流されにくくなり、「自動的な反応」から「意図的な選択」への転換が起こることが分かっています。
コーチングによる効果として自身の内面に起きるモノゴトを客観的に捉える思考を育てています。
② 安全な関係性が報酬系を動かす
人は、緊張や萎縮する感覚を得ると防御するほうに多くのエネルギーが使われてしまいます。
一方、安心して話せる関係性があると、脳は「心地よさ」を感知してリラックスした状態を維持しようとする働きがうまれます。
ドーパミンやオキシトシンなどの神経物質が働き、挑戦や変化に対する恐怖がやわらぎ、より自由な発想にエネルギーを注ぐことができます。
人は、安心感があることで、脳は「変化=危険」ではなく「変化=学び」と認識します。
コーチが評価や結論を急がず、相手の話を受け止める理由はここにあります。
③ 意味づけの変化が神経回路を再構築する
脳には「神経可塑性」と呼ばれる性質があります。
これは、学習や経験によって神経細胞のつながりが変化する仕組みです。
私たちは、日常的に経験学習を重ねて過去の情報をつくり替えています。
この仕組みを活かしているのがコーチングの対話です。
対話を通じて過去の経験の意味づけが変わると、脳の中では古い結びつきが弱まり、新しい結びつきが形成されます。
たとえば、「失敗=価値がない」という思い込みを「失敗=学びの素材」と言い換えられたとき。
脳は新しい情報処理の経路を作ります。この神経の再編成が、新しい行動を支える基盤になります。

動きたいのに「動けない」と語られれる背景 ― 知覚と認知と認識ズレ
やらなければならないと頭ではわかっているのに体が動かない。
やりたいと思っているのに、実際には動けない。
そう語られる場面は、少なくありません。
どうしてこんな現象が起きるのでしょうか。
「やっていることが、いまのあなたが“本当に選んでいること”ですよ」と伝えると、感情的な反応を見せる方もいます。
この「動きたいけれど動けない」背景には、脳の情報処理の仕組みが関係しています。
コーチングは、脳内で起きる知覚・認知・認識のズレを整え、行動につなげていきます。
私たちの脳は、刺激を受け取り(知覚)、それを解釈し(認知)、意味を理解する(認識)という順番で処理しています。処理手順は、すでに備えている情報によって何を取捨選択するかなど無意識化で勝手に行われています。
知覚:外界や内面の刺激を感覚器で受け取る
認知:情報を経験や記憶と照らし合わせ、意味づけや判断を行う
認識:意味が確定し、「そうだったのか」と理解に変わる
理性的な判断を行う前頭前野と、感情を司る扁桃体は、しばしば拮抗して働きます。
不安や恐怖を感じると扁桃体が活発になり、前頭前野の働きが抑えられるため、認知とズレた状態になります。
行動の方向に不安や怖さがある場合、人は現状を維持しようとします。
逆に、立ち止まることに不安がある場合は、考える前に動き続けてしまう。
どちらも、知覚・認知・認識のタイミングがずれた結果として起きる反応です。
コーチングでは、クライアントが抱える感情を言葉にし、その背景を一緒にみていきます。
「怒りがあった」「怖かった」と言語化するだけでも、扁桃体の反応は落ち着くことが確認されています。
感情を言葉にして、納得や理解が進むと、思考が再び働き始め、状況を客観的に判断できるようにもなります。
感情を理解し、認知と統合すると、行動は自然に動き出します。
コーチングは、その「統合の場」をつくる実践です。
行動を支える「しくみ」をつくる ― 行動科学の視点
人の行動には「きっかけ」「行動」「結果」という条件があり、それぞれのバランスが取れたときに継続が生まれます。
コーチングは、この条件を整えることで、行動を一時的なものではなく、再現できる行動習慣へと変えていきます。
① ABC理論 ― 行動の条件づけを再設計する
行動分析学では、人の行動は以下の3つで構成されると説明されます。
| 要素 | 内容 | コーチングでの支援 |
|---|---|---|
| A(Antecedent:きっかけ) | 行動を起こす前の状況や認知 | 目的設定・環境づくり・トリガーの意識化 |
| B(Behavior:行動) | 実際の行動 | 実行の支援・行動の見える化 |
| C(Consequence:結果) | 行動の結果・フィードバック | 振り返り・承認・学習の強化 |
人は「行動した結果、良いことがあった」と感じたときに、その行動を繰り返します。
コーチングでは、行動した後に「どう感じたか」「何を得たか」を振り返り、言葉にしていきます。そして、その行動を再現させるのか、あるいは制御するのか。自分にとってどうだったかの再解釈が行われ、次の行動への動機を強化していきます。
② Foggの行動モデル ― 行動が起こる3つの条件
スタンフォード大学の行動デザイナー、BJ・フォッグが提唱したモデルによると、
行動が起こるには次の3条件が揃う必要があります。
| 条件 | 内容 | コーチングでのアプローチ |
|---|---|---|
| Motivation(動機) | 行動したい、必要だという感情的な理由 | 目的を言語化し、内発的動機を引き出す質問 |
| Ability(能力) | 実行できると感じる自己効力感 | スモールステップの設計とリソース確認 |
| Prompt(きっかけ) | 行動のトリガー | 行動宣言やフォローアップでタイミングを整える |
たとえば「明日から運動する」と決めても、
動機が弱い、時間がない、きっかけが曖昧であれば行動は起きません。
意志ではなく構造を変える。
それが、行動科学に基づくコーチングの特徴です。
書籍:習慣超大全——スタンフォード行動デザイン研究所の自分を変える方法
③モチベーション理論 ― 行動を生み出す3つの条件
モチベーションとは、条件がそろったときに高まる心理的なエネルギーのことです。
人は意志の力だけで動くのではなく、内側に「動きたい理由」が整ったときに自然と行動を起こします。
その構造を、ここでは「欲求 × 動機 × ビジョン」で整理します。
| 要素 | 内容 | コーチングでのアプローチ |
|---|---|---|
| 欲求(Need) | 満たしたい・実現したいという自然なエネルギー。マズローの欲求5段階で説明される人間の基本的な原動力。 | 現在どんな欲求が満たされ、どんな欲求が満たされていないのかを整理し、行動の源泉を明確にする。 |
| 動機(Motive) | 欲求が具体的な行動に変換される理由。「なぜそれをしたいのか」という意味づけ。外発的動機(報酬や承認)と内発的動機(興味や価値観)がある | 「何のために」「どんな意味があるか」を問うことで、外的動機から内的動機へと転換を促す。 |
| ビジョン(Vision) | 行動の方向性や目的地。自分がどうありたいか、何を実現したいかという将来像。 | ビジョンを言語化し、現在の行動とつなげる。短期目標ではなく長期的意義を描く支援を行う。 |
これら3つの要素が重なったとき、人のモチベーションは最も高まります。
この3条件が整うことで、モチベーションは外から与えられるものではなく、内側から自然に立ち上がる力へと変わります。
📘 補足:自己決定理論(Self-Determination Theory)との関連
心理学者デシとライアンによる自己決定理論では、人が自ら動くためには次の3要素が満たされる必要があるとされます。
- 自律性:自分で選んでいると感じること
- 有能感:できるという感覚を持つこと
- 関係性:人とのつながりを感じること
これらは、動機を外的から内的へと変える条件でもあります。
つまり、モチベーションは「欲求 × 動機 × ビジョン」が整うと同時に、この3要素が支えとなって強く、長く持続します。
人が変わるには段階がある ― 変化のプロセスに寄り添う
行動変容は、一瞬で起こるものではありません。
人は「気づく」「準備する」「行動する」「続ける」という段階を踏んで変化します。
心理学者プロチャスカらが提唱した「行動変容ステージモデル」では、人の変化は次の5段階で進むとされています。
- 無関心期:変わる必要を感じていない
- 関心期:変わる必要を意識し始める
- 準備期:行動するための方法を考える
- 行動期:実際に行動を始める
- 維持期:行動を習慣化し、安定させる
コーチングは、相手の状態を見極めて必要な関りを行っています。関心期では「気づきを促す問い」、関心期では「目的の明確化」、準備期では「計画と環境づくり」、行動期では「実行支援」、維持期では「振り返りと自己評価の確認」。
ことばが行動を変える ― 言語の力とコーチング
人は、話すことで考えが整理されることがあります。
頭の中で、考えている曖昧なことを一旦「ことば」を活用してカタチにする。
コーチングにおけるかかわりは、「言語化」を促しながら、考える力、創造する力を育み、内面と行動の一致を促進していきます。
① スピーチアクト ― 発話は「行為」である
言語学者ジョン・オースティンとジョン・サールは、「発話は情報伝達ではなく、行為である」と述べました。
たとえば、「約束する」「宣言する」「お願いする」といった言葉は、それを発すること自体が行動になります。
コーチングにおける「質問」も同じです。
「何を大切にしたいですか?」という問いは、相手に考えさせる行為であり、その瞬間に内的な探索が始まります。ことばを発するたびに、人の内面では新しい意味づけが生まれています。
書籍:言語と行為 いかにして言葉でものごとを行うか
② ナラティブ ― 経験を語り直すことで意味が変わる
心理学では、自分の経験を語ることを「ナラティブ(物語化)」と呼びます。
人は、出来事を事実のまま記憶しているわけではありません。
出来事を経験した瞬間に、すでに「自分なりの解釈」を加えて記憶しています。
そして、その出来事を語るたびに、記憶は再構築されます。
人は「何を語るか」だけでなく、「どう語るか」によって、過去の出来事の意味を作り変えている。
コーチングの場で過去の経験を話すとき、この再構築のプロセスが自然に起こります。
「なぜあのときうまくいかなかったのか」「本当はどうしたかったのか」と語り直すことで、
その出来事に対する解釈が変化します。
たとえば、失敗体験が「自分には向いていない証拠」から「成長の材料」へと書き換えられる。
この意味の変化が、新しい行動を生む起点になります。
言葉は、自分の考えを整理し、新しい理解を形づくるための道具です。
語り直すことによって、人は「自分が何を感じ、どう受け止めていたのか」を整理し直し、
その理解が行動の変化へとつながっていきます。
③ 言語化が生む自己一致
言語化によって内面と行動がかみ合い、自分の中に一貫性が生まれます。
心理学ではこれを「自己一致」と呼び、自己一致が進むほど迷いが減り、行動が自然に定まっていきます。
コーチングは「自らが自分を変化させる力を育む」
コーチングで行動変容が起きるのは、単なる励ましや意識づけではありません。
- 思考・感情・信念という内側の構造を理解し、整える。
- 安全な関係の中で、脳が学び直す環境をつくる。
- 行動を支える条件を整え、小さな成功体験を重ねる。
- 言葉を通して意味を再構築し、自分を納得させる。
これらがそろったとき、人は自然に行動を変えることができます。
コーチングとは、「相手を動かす技術」ではなく、
人が自分で変わる力を取り戻すためのプロセスだと私たちは、考えています。
前の記事:コーチングとはなにか