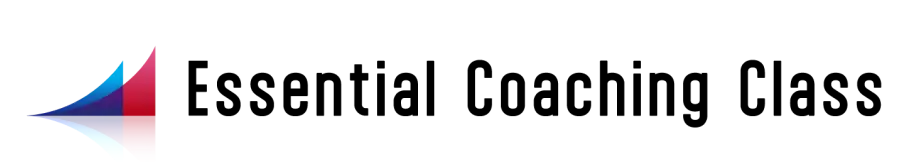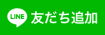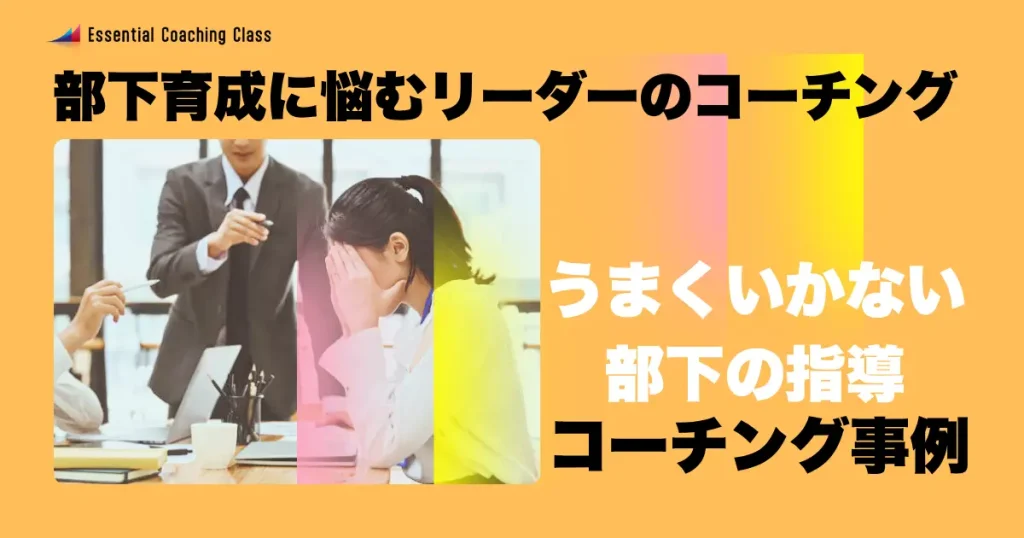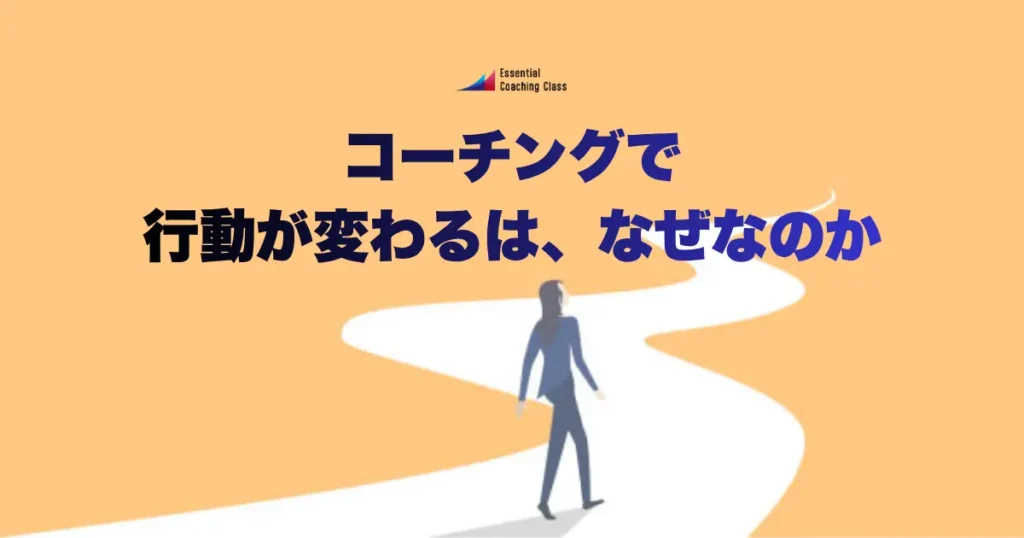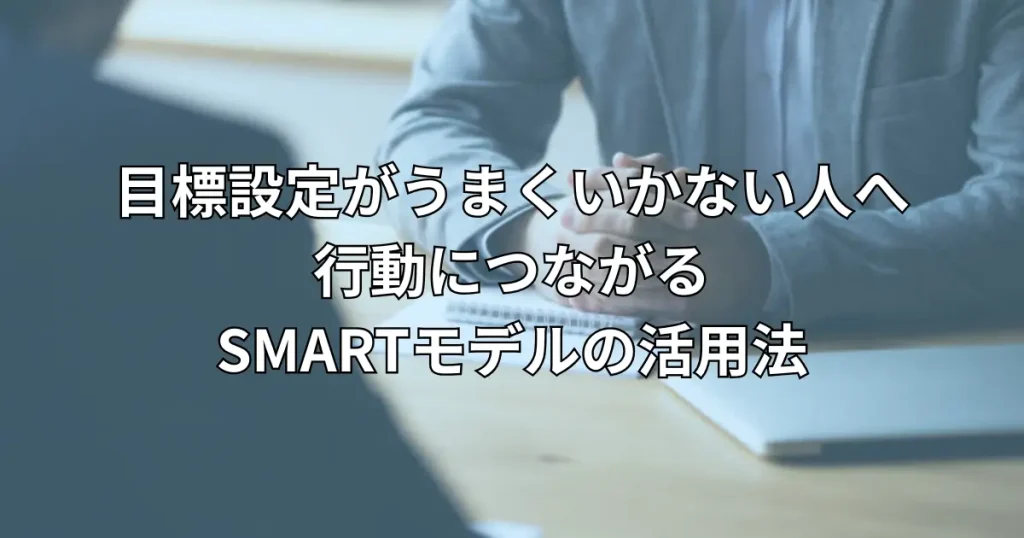リーダーの内面から変化を起こすコーチングの実践
こんにちは、コーチの鈴木です。
普段、私は多くのリーダーの方々から寄せられる、部下育成に関するご相談に伴走しています。その中で最も多い悩みの一つが、
- 「部下に仕事を任せても、期待通りに動いてくれない」
- 「何度言っても、同じミスを繰り返す」
- 「なぜ、わからないことを聞いてこないのだろう?」
といった、部下とのコミュニケーションにおける根深いジレンマです。
コーチングを学ぶ皆さんの中にも、こうしたリーダーの悩みに向き合う場面は多いのではないでしょうか。そして、その真摯な悩みを聞くうちに、「なんとかしてあげたい」という思いから、つい「もっと具体的な指示の出し方を試してみては?」「1on1の時間を増やしてみてはどうでしょう?」といった、具体的な解決策やHOW(方法論)を提示したくなった経験はありませんか?
もちろん、それらが有効な場合もあります。しかし、多くの場合、それは一時的な対症療法に過ぎず、リーダーの根本的な悩みは解消されません。なぜなら、問題の本質は部下のスキルや意欲だけにあるのではなく、リーダー自身の「物事の捉え方」や「関わり方のスタンス」に隠されていることが多いからです。
今回は、部下への尽きない「モヤモヤ」を抱えていたリーダーのAさんとのセッション事例をもとに、小手先のテクニックではなく、リーダー自身の深い「内省」を促し、自発的な行動変容を生み出すコーチングの関わり方について、私の視点からお伝えしていきたいと思います。
陥りがちな「問題解決型コーチング」の罠
リーダーであるAさんとのセッションは、「部下への期待と、上がってくるアウトプットのギャップに悩んでいる」という、非常に切実なテーマから始まりました。
顧客とのミーティングを任せても的確に答えられない部下。
事前に「わからないことは何でも聞いて」と伝えているのに、なぜか聞いてこない部下。
Aさんの言葉の端々からは、「自分はやるべきことをやっているのに、なぜ相手は応えてくれないのか」という、もどかしさが感じられました。
このような状況でコーチが陥りがちなのが、「問題解決型」のアプローチです。
例えば、
- 「どんな質問をされると答えに詰まるのですか?(原因分析)」
- 「どのような指示をだしたのですか?(現状の行動確認)」
- 「ロープレをしてみるとかはどうでしょう?(解決策の提案)」
といった関わり方です。
これらは一見、クライアントに寄り添い、具体的な行動を促すための有効な質問のように思えます。しかし、これらのアプローチには大きな落とし穴があります。それは、コーチとクライアントの意識が「いかにして部下を変えるか」という、クライアントの外側にある問題に集中してしまうことです。
この関わり方を続けると、セッションは「部下を動かすためのHOW探し」の場になってしまいます。
コーチングは、HOW探しではありません。なぜなら、HOWのやり方を提供してもAさん自身のリーダーとしての成長には繋がらないからです。
リーダーとして、自らの課題を解決し、成長するための支援には、視点を180度転換する必要がありました。
「違和感」の言語化をうながし、解像度をあげる
私がAさんの話を聞きながら最も注目したのは、Aさんが何度も口にしていた「モヤモヤする」「なんだか違和感がある」という、ご自身の「感情」でした。問題や出来事そのものではなく、それに対してクライアントが「何を感じているのか」。ここにこそ、問題の本質に迫るヒントが隠されています。
そこで私は、Aさんの内側で起きていることにフォーカスして、次のような問いを投げかけました。
「そもそも、Aさんが感じていた『メンバーに教えることへの違和感』って、どんな違和感だったんでしょう。」
この問いは、Aさん自身の「内面」を言語化するためのものです。具体的なHOWを求めるのではなく、Aさん自身の無意識を言葉にする。自分の内面に意識をむけて意図的に、言語化していくプロセスを体験してもらうことが目的でした。
しばらくの沈黙の後、Aさんはゆっくりと話し始めました。その表情は、必死に答えを探すというよりも、ご自身の感覚を丁寧に確かめているように見えました。
「そうですね…。話している中で、その違和感が少し整理できたかなと思います。一つは、相手のアウトプットと私の期待とのズレからくる違和感。もう一つは、自分がこれまで教えてきたのに、相手が覚えていないことへのイラだち。大きくはこの二つなのかなと」
Aさんは、漠然としていた「モヤモヤ」の正体を、「期待とのズレ」と「記憶の欠如への不満」という、二つの具体的な要素として表現してくれました。
クライアントの内側で起きた「リフレーミング」
一度、自分の中で課題が整理されると、「リフレーミング(問題の捉え直し)」が起こります。
まず、一つ目の「期待とのズレ」について、Aさんはこう続けました。
「今日お話しして考えたのですが、前者(期待とのズレ)については、私の側の問題ですね。そもそも『どうなってほしいか』という期待の解像度が低かったり、その仕事の背景にある意図…例えば『お客様にはこうしてほしい、なぜならこういう意図があるから』という部分まで、自分でも噛み砕けていないから、相手にも伝わっていない。だから、部下もできない、という状況になっているのかなと思いました」
「部下が期待に応えてくれない」という他責の視点から、「自分の期待の伝え方が不十分だった」という視点へ。問題の捉え方が180度転換した瞬間でした。
さらに、二つ目の「覚えていないことへのモヤモヤ」についても、Aさんの視点は変わります。
「後者については、そもそも部下側も『何がわからないのかが、わからない』状態なんだろうなと。『言ったのになんで覚えていないの?』と感じるのは、私と部下とでは、重要だと捉えてピックアップしている事象や、記憶に残している単語、理解している文脈が違うからなんだろうなと思いました」
これは、単に部下を責めるのではなく、「なぜそうなってしまうのか」を相手の立場に立って想像しようとする、共感的な視点の獲得です。この気づきから、Aさんは自然と次のアクションを見出しました。
「だからまず、部下が今わかっていることを全部出してもらって、『ここの認識は合っているね』『あ、ここが足りなかったんだね』というのを、お互いにチェックしないと分からない話なのかな、と」
「教える」「指示する」という一方通行の関係性から、「お互いに確認し合う」という双方向のコミュニケーションへと、関わり方のスタンスそのものが変化しました。
部下の行動は、自分を映し出した「鏡」
Aさんの気づきは、問題の核心にたどり着きます。それは、テクニックや方法論をはるかに超えた、リーダーとしてのあり方そのものに関する、気づきでした。
「だから本当に『鏡』だな、と。相手が丁寧じゃないなと感じる時は、きっと自分が丁寧じゃなかったんだなって、すごく思いました。『もうちょっと丁寧にやってよ』と思うなら、こちらがもっと具体的に教えてあげないと、丁寧にはならないんだな、と」
Aさんは、部下の姿を通して、自分自身の関わり方を見ていたのだと気づいたのです。部下の行動は、Aさん自身の行動や姿勢を映し出す鏡である。この認識は、今後のAさんのリーダーとしての行動すべてに展開されていくと感じました。
さらに、Aさんはご自身の思考のクセにまで気づいていきます。
「全体的なモヤっと感って、一つ一つの業務の中での『あれ?』っていう小さなモヤりの積み重ねで、『この子にこの仕事を任せるのは、まだ早かったかな?』という、私のジャッジになってしまっていた気もします」
これは、自分が無意識のうちに部下を「できない」と決めつけ、評価(ジャッジ)してしまっていたという、自分自身の思考プロセスへの「メタ認知」です。
ここまで内省が深まると、もはやコーチからの「どうしますか?」という問いは不要です。Aさんの内側から、自然とエネルギーと行動への意欲が湧き上がってくるからです。「部下をどうにかしたい」という悩みから始まったセッションは、Aさん自身の「自分は明日からどうあろうか」という、リーダーとしてのありかたに変化していました。
内省を促すコーチングの具体的アプローチ
Aさんとのセッションは、コーチングを学ぶ私たちに、非常に重要な示唆を与えてくれます。それは、問題解決のHOW(方法論)をクライアントに与えることではなく。クライアントが自分自身の言動の背景に気づくこと。そして言葉にして向き合い、問題の捉え方そのものを変容させるプロセスを伴走する、ということです。
リーダーの内省を促し、行動変容を生むコーチングのポイントは、以下のように整理できるでしょう。
1.「事実」ではなく感情に注目する 「違和感」「モヤっとした感情」など、クライアントが表現する感情的な言葉を丁寧に拾い上げ、その正体を探求する質問を投げかける。
2.安易にアドバイスをしない:コーチが答えを知っているというスタンスを手放し、クライアントが自ら言語化し、気づきを得るプロセスを辛抱強く信じて待ちます。
3.相手の立場に立つ視点を促す: 「部下の立場から見たら、どう感じるでしょうか」「部下にとって、どのような状況なのでしょうか」といった問いかけで、相手の視点を促す。
4.構造的な理解を促す: 個別の事象ではなく、「なぜこのような状況が生まれるのか」という構造的な理解を促す質問を投げかける。
まとめ ~内省から生まれる持続的な変化~
部下育成に悩むリーダーのコーチングにおいて、「HOW」を教えることは一時的な解決策にしかなりません。しかし、リーダー自身が、自分の無意識を言語化することで、自分の関わり方に気付くことができます。気づきをもとに関わりを選択することで、変化を起こすことができるのです。
コーチとしての私たちの役割は、答えを与えることではなく、クライアントが自分自身で答えを見つけられるように支援することです。
時間はかかるかもしれませんが、Aさんのように、自分の内側を変化させられるリーダーは、今後あらゆる場面で相手との関係性を柔軟に改善していくことができます。もし、普段のコーチングでHOWにフォーカスしているのでしたら、本コラムの内容を試してみてください。

執筆・編集
鈴木 敦子
株式会社Starting Point 代表取締役
エグゼクティブコーチ
組織開発コンサルタント
エッセンシャルコーチングクラスについて
当スクールのコンテンツは、講師陣が20年以上の実践で成果を出し続けた内容を盛り込んでいます。実際の現場で、活用独自プログラムを提供しています。
<手に入る三つの成果>
1.なりたい自分になる方法
自分の内側に発生する感覚を捉え、言語化していくエクササイズを多数用意しています。クラスで学びあうプロセスを経て、なりたい自分になるための手法を習得してもらいます。
2.継続的な成長を実現する習慣
コーチングを習得する過程を経て、進化し続ける習慣を醸成していきます。7カ月の学習期間は、対面学習だけでなく、オンラインでの振り返りがあります。そして毎月の課題に取り組むことで、自身をバージョンアップし続けることができます。
3.継続的な成長を支えるチーム
私たちの学習コミュニティは、関係そのものを変化させることにフォーカスしています。そのため、協力、共感、協調、協働が自然と育まれます。共に成長し続けるチーム感を体感してしていただきたいと考えています。。
効果的なチームワークは、個々の能力を超えて目標を達成する傾向があります。それは、力強い味方となるでしょう。クラス修了しても成長し続ける関わりが手に入ります。