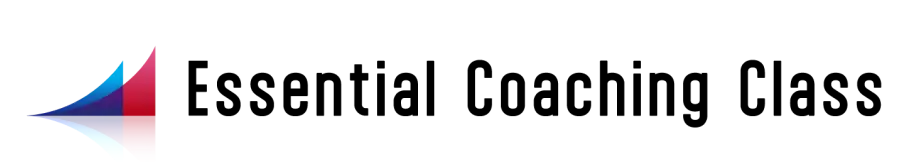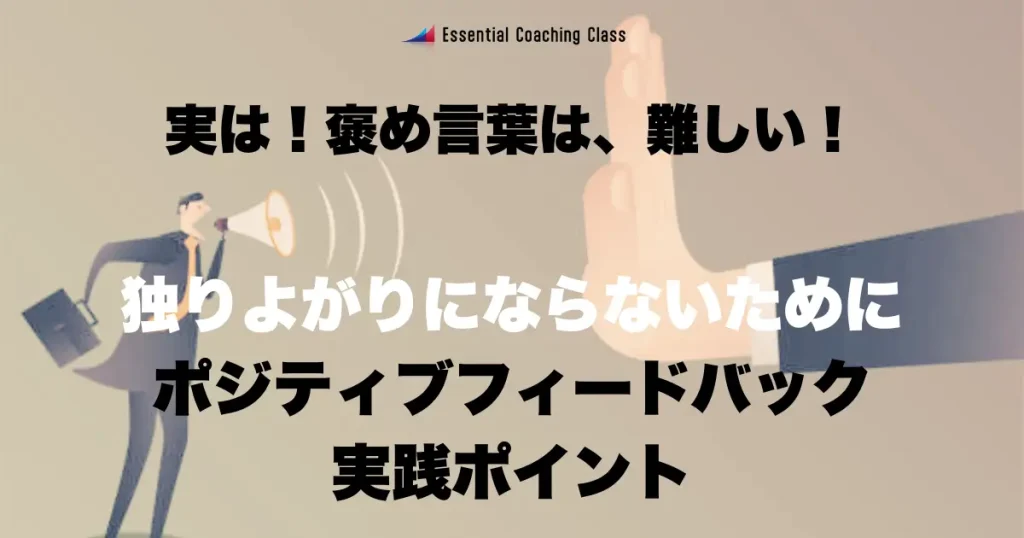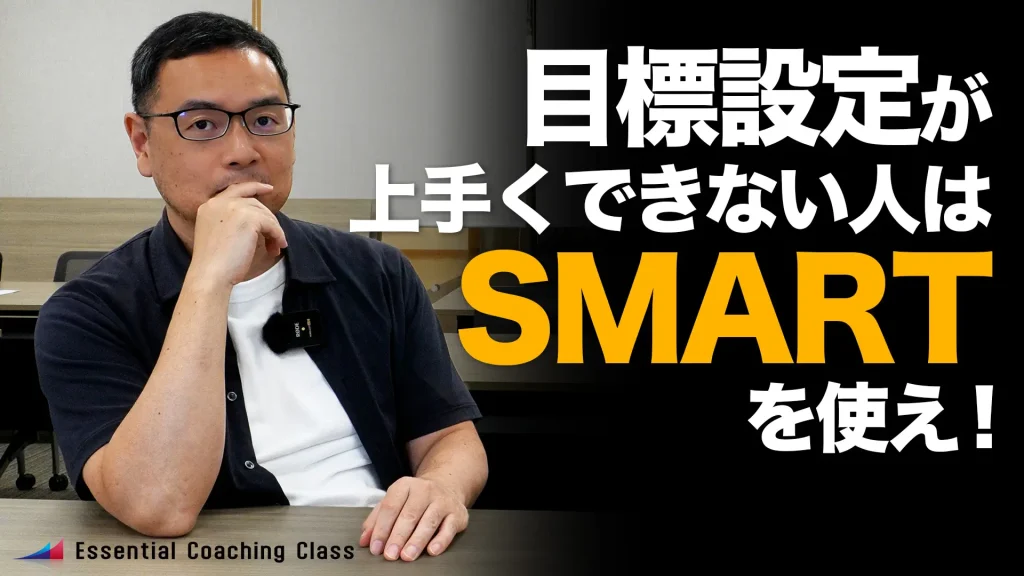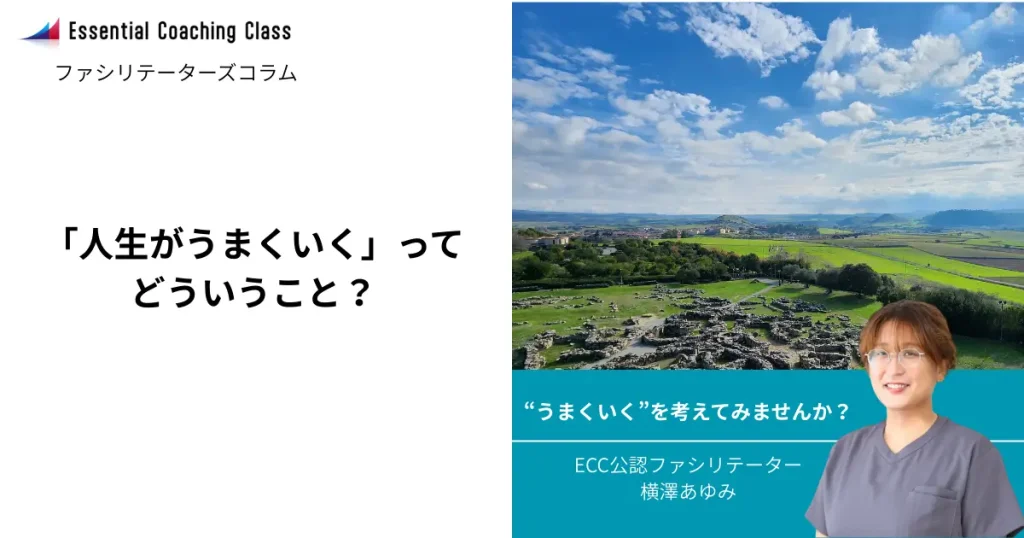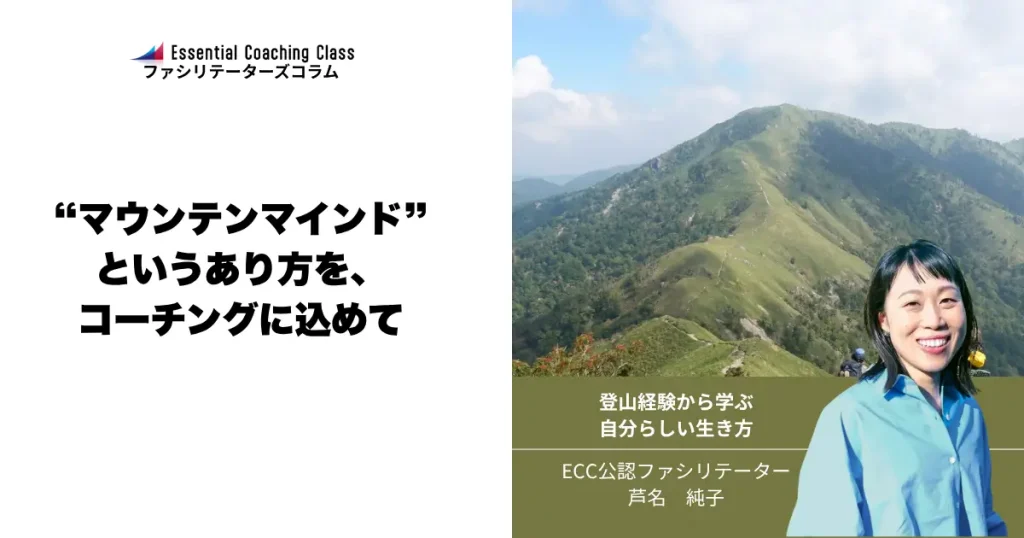エッセンシャルコーチングクラスの鈴木です。
「ポジティブフィードバックは簡単なようで、難しい。」これは常々感じていることですが、先日のセッションでも実感したました。
ネガティブなフィードバックは誰もが身構えます。どう伝えようか、どの言葉を選べば角が立たないか、と緊張します。一方でポジティブなフィードバックは「良いことを伝えるだけだから簡単だろう」と思われがちです。ところが実際には、受け手に響く言葉を届けるのは想像以上に難しいものです。
上司からの「責任感があるよね」が、まったく響かなかった
クライアントとのセッション後の雑談で気になる話しがありました。上司から評価面談の時間。ポジティブな側面として「あなたは責任感があるよね」と言われたけど、まったく響かなかったというのです。
一見、褒め言葉であり、良い表現です。しかしその方はなぜかピンと来なかった。どういうことでしょうか。
そのピンとこない背景を一緒に振り返ってみました。すると「そんなのは仕事だから当たり前じゃないか」「みんな責任感はあるのでは?」という思いが湧いてきたそうです。つまり、その言葉が自分だけに当てはまる独自性や、自分が大切にしてきた努力や成長とつながらなかったといいます。
「責任感」という抽象的な言葉は一般的すぎて、本人の強みや差別化を浮き彫りにしません。どのような表現であれば、ポジティブなフィードバックとして受け取れたのか。単なる形容詞ではなく「なぜそのように感じたのか」を示す具体的なエピソードがあったら、嬉しかったと話されていました。
簡単なようで、実は難しい。
ポジティブフィードバックを行う際に意識すると良いポイントをご紹介します。
ポジティブフィードバックに必要な5つのポイント
「どうすれば相手に届くフィードバックになるのか」という観点から、5つのポイントを整理してお伝えします。目的は、単なる表面的な称賛ではなく、相手の成長や自信を支える力強いメッセージに変えていくことです。
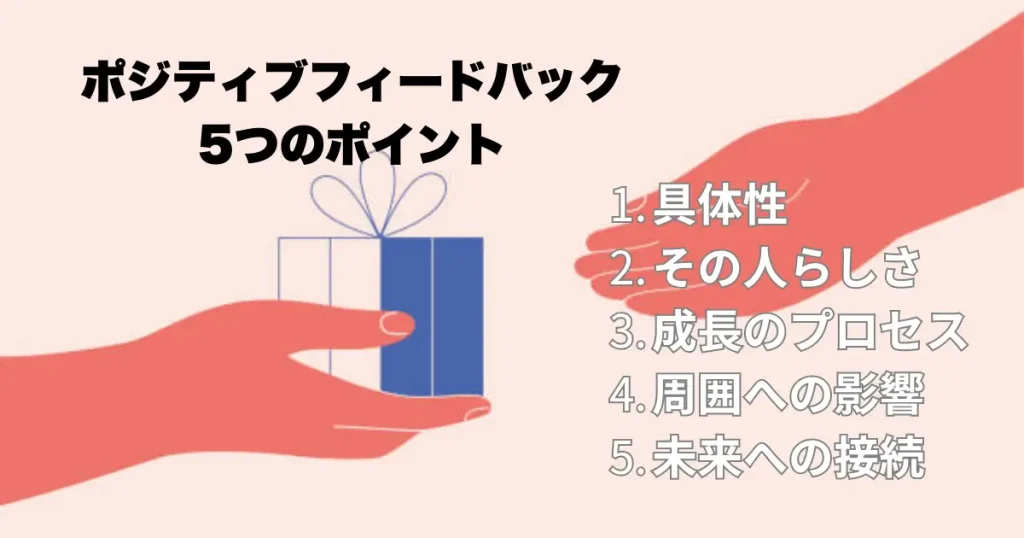
1. 抽象ではなく具体で伝える
「責任感がある」だけでは一般論としか伝わりません。
たとえば「〇〇のプロジェクトでは、締切が厳しい中大変だったね(労い)。積極的にメンバーに声をかけていたね(行動承認)。タスクを前倒しで仕上げてくれて〇〇の部門も助かったと言っていたよ(影響)。あのときの一連からも、自分事で行動できている。責任感を強く感じた。」
このように、具体的な行動と文脈を示すことで、相手は自分のどの行動が認められたのか理解できます。記憶とつながる具体例は、心理学的にも受け手の納得感を高めます。
2. その人らしさを伝える
「みんな頑張っているけど、あなたは特にこういう工夫をしていたよね」
こうした言葉は、その人固有の強みを際立たせます。他の誰にでも当てはまる一般的な言葉よりも、本人だけが持っている「らしさ」を見つけて伝える方が、承認の力は大きくなります。
組織心理学ではこれを「ユニーク・バリュー認知(※)」と呼び、人のモチベーションを大きく高める要因とされています。
※ユニークバリュー認知とは、その人だけが持つ独自の強みや価値を周囲から承認されることです。
3. 成長のプロセスを承認する
「最初は戸惑っていたのに、工夫を重ねて成果を出すようになったね」AだったのにBになった(変化)
このように努力や学習の軌跡を承認すると、受け手は「自分の挑戦がちゃんと見られていた」と感じ、強い励ましにつながります。
自己決定理論においても「有能感の承認」が内発的動機づけ(※)を育むことが指摘されています。
※内発的動機づけとは、報酬や評価ではなく「やりたい・面白い・成長したい」という内側から湧く意欲によって行動することです。
4. 周囲への影響を伝える
「あなたが責任を持って動いてくれたおかげで、チーム全体が安心して進められた」
このように、自分の行動が周囲にどんな価値をもたらしたかを伝えると、「自分はチームに貢献している」という実感が生まれます。人は自分の影響力を実感したときに最も大きな充足感を得るのです。
5. 未来に接続するフィードバック
「この強みを活かして、次はさらに大きなプロジェクトでリードしてみてはどうか」
単なる称賛で終わらせず、未来への挑戦や可能性につなげることで、フィードバックは「成長の方向性」を指し示す道標となります。
これは単なる評価ではなく、本人のキャリアを広げる伴走メッセージになります。
ポジティブフィードバックは相手が良い印象として受け取れるか
ポジティブフィードバックは、表面的に言葉を並べるだけでは空虚なものになります。むしろ「褒めているつもりなのに、相手が白けてしまう」という逆効果もあり得ます。
一方で、具体性・固有性・成長の承認・影響の提示・未来への接続があるフィードバックは、受け手にとって大きな贈り物になります。自分が見てもらえている実感、努力が意味を持ったという感覚は、人の自己効力感やエンゲージメントを大きく高めます。
だからこそ、「良いことを言えばいい」ではなく「どう伝えると相手に響くか」に丁寧に向き合う必要があります。
まとめ
ポジティブフィードバックを効果的に届けるためのポイントは次の5つでした。
- 抽象ではなく具体で伝える
- その人らしさを伝える
- 成長のプロセスを承認する
- 周囲への影響を伝える
- 未来に接続する
これらを意識することで、フィードバックは単なる「お世辞」や「慣用句」ではなく、相手の内面に届く力強いメッセージになります。
そして、それができるようになるためには、普段からの準備が欠かせません。具体的には:
- 観察力を養う:日常の小さな行動や変化をよく見る習慣を持つ
- 言葉の引き出しを増やす:読書や日記、語彙を広げる取り組みを続ける
- 表現力を鍛える:感じたことを具体的に言葉に置き換える練習をする
これらの積み重ねが、相手に響くフィードバックを支える土台になります。
最後に大切なのは――相手に響かなかったら、意味がないということです。
フィードバックを伝える際に「この言葉は相手にどう影響したのか」を確認しながら関わっていくこと。ですが、推測するにも限界があります。「どのように伝わったのか」を相手にズバッと聞いてしまうのも一つです。
あるいは、普段どのようなフィードバックなら嬉しいかを聞いてみてください。
目的や意図から外れてしまうことが一番もったいない。
常に相手と調整しながら育むことが最大のポイントだと私は考えています。

執筆・編集:鈴木敦子
エッセンシャルコーチングクラスについて
当スクールのコンテンツは、講師陣が20年以上の実践で成果を出し続けた内容を盛り込んでいます。実際の現場で、活用独自プログラムを提供しています。
<手に入る三つの成果>
1.なりたい自分になる方法
自分の内側に発生する感覚を捉え、言語化していくエクササイズを多数用意しています。クラスで学びあうプロセスを経て、なりたい自分になるための手法を習得してもらいます。
2.継続的な成長を実現する習慣
コーチングを習得する過程を経て、進化し続ける習慣を醸成していきます。7カ月の学習期間は、対面学習だけでなく、オンラインでの振り返りがあります。そして毎月の課題に取り組むことで、自身をバージョンアップし続けることができます。
3.継続的な成長を支えるチーム
私たちの学習コミュニティは、関係そのものを変化させることにフォーカスしています。そのため、協力、共感、協調、協働が自然と育まれます。共に成長し続けるチーム感を体感してしていただきたいと考えています。。
効果的なチームワークは、個々の能力を超えて目標を達成する傾向があります。それは、力強い味方となるでしょう。クラス修了しても成長し続ける関わりが手に入ります。